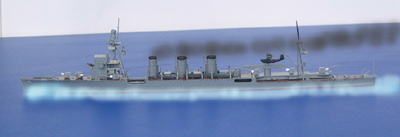日本海軍 巡洋艦・駆逐艦
軽巡洋艦 熊野
最上型の4番艦として1934年4月5日、川崎重工業神戸造船所にて起工。1936年10月15日に進水し、1937年10月31日就役する。
同型の姉妹艦には「最上」「三隈」「鈴谷」がある。
当初は主砲に15.5cm3連装砲5基を持つ、軽巡洋艦として建造されたが、これはロンドン軍縮条約失効後を見越し、後に20.3cm連装砲塔に換装し、重巡洋艦に変更するためであり、ロンドン軍縮条約の規定に基づき、保有枠のまだある軽巡洋艦の扱いで建造するための偽装であった。
このため、15.5cm3連装砲を採用したが、装換された15.5cm砲は大淀の主砲や大和型戦艦の副砲に使用された。
基準排水量8500tも保有枠に基づいての要求仕様であるが、15.5cm3連装砲は重巡洋艦の20.3cm連装砲よりも重量が大きいため、排水量は12000tにも達していた。
全長は200.6 m、これは立派な重巡洋艦である。
開戦前に20.3cm連装砲に換装し、マレー上陸作戦、バタビア沖海戦、ミッドウェー海戦に参加。ミッドウェー海戦で姉妹艦「最上」と「三隈」が衝突し、「三隈」が沈没、「最上」が大破。
「最上」はこの損傷により航空巡洋艦に改装される。
なお、15.5cm三連装砲は、砲弾一発あたりの威力では劣るものの、単位時間あたりの投射砲弾重量では20.3cm連装砲より勝っており、実質、軽巡洋艦時の方が使い手が良かったという。
デザイン的にも軽巡洋艦時の方がすっきりとしていて優れる。
ミッドウェー海戦後、インド洋での通商破壊作戦、第二次ソロモン海戦、南太平洋海戦、マリアナ沖海戦に参加、大きな被害は受けなかった。
しかし、1944年10月25日のサマール島沖海戦で米駆逐艦ジョンストンの雷撃を受け損傷。11月25日、日本本土への回航中に米艦載機の攻撃により沈没。
その詳細は
http://www2u.biglobe.ne.jp/~surplus/tokushu43.htmに詳しい。


防空巡洋艦 五十鈴
旧式の軽巡洋艦を防空巡洋艦に改造した船である。
大正時代、第一次世界大戦後に多数建造された5500トン型軽巡洋艦の長良型の一艦として、1923年(大正12年)に完成した。
完成時には、高速軽巡洋艦として、水雷戦隊の旗艦であった。
歴代艦長には山本五十六、高須四郎、山口多聞などが名を連ねる。

太平洋戦争開戦時にはすでに旧式化していたが、開戦時には最前線ではなく香港攻略戦に参加した。
1942年4月10日、第2南遣艦隊第16戦隊に編入され、小スンダ列島攻略戦などに参加。
ソロモン諸島方面で激戦に参加、しかし、第2水雷戦隊の旗艦となり、南太平洋海戦と第三次ソロモン海戦に参加。
後者では第三次ソロモン海戦では大破、復旧以後は輸送や救援活動に従事。
1943年12月5日、ルオットでアメリカ機動部隊の空襲で損傷し日本に帰還。

その修復において防空巡洋艦に改造され、主砲7門をすべて八九式12.7cm連装高角砲3基6門に換装。
姉妹艦で防空巡洋艦に改造されたのは五十鈴のみであった。
また、対潜装備も増備され、改装中に対潜掃討部隊の第31戦隊に当初予定されていた「名取」に代わって旗艦として編入された。
五十鈴が対潜掃討部隊に編入されたのは、名取より電探や対潜兵器が充実していたからであった。
改装後、小沢中将指揮の第三艦隊の一員としてレイテ沖海戦に投入された。
この海戦において、防空巡洋艦の性能を発揮し13機を撃墜。

レイテ沖海戦後、フィリピン方面への輸送任務に従事するが、1944年11月19日、コレヒドール島沖で米潜水艦「ヘイク」の雷撃で大破。
シンガポール、ついでスラバヤで修理を行う。修理後、ティモール島をはじめとするスンダ列島所在の陸軍部隊を撤退させる「二号作戦」に参加。
陸軍部隊を輸送中、4月6日、9機のB-24と39機のB-25の攻撃を受け、至近弾数発のほか艦首に爆弾1発が命中(不発)するが、3機を撃墜し、任務を完了。
4月7日早朝、米潜水艦「ガビラン」 から1本、「チャー」 から3本の魚雷を受け沈没した。
利用範囲が限定される旧式の軽巡洋艦を上手く転用再利用したものであり、目的どおりの性能を発揮したと言えるだろう。(Wikipedia参照)
性能諸元
排水量 基準:5,170トン 全長 162.15m
全幅 14.17m 機関 90,000馬力 最大速 36.0ノット
乗員 440名
防空巡洋艦に改装後 40口径八九式12.7cm連装高角砲 3基6門
九六式25mm3連装機銃 11基33門 同単装機銃 5基5門
九二式4連装魚雷発射管 2基8門 水中探信儀 水中聴音機
爆雷投射機 爆雷投下軌条 2基 爆雷 90個
21号電探 1基 22号電探1基 13号電探 1基
軽巡洋艦 鬼怒
3本煙突の特徴あるシルエットを持つ軽巡洋艦でイギリスの巡洋艦と良く似る。
同じ軽巡洋艦の矢矧や大淀などの洗練されたシルエットから比べるといかにも時代遅れのような感じを受ける。
それもそのはずモデルはイギリスの巡洋艦そのものであり、竣工が大正11年というからちょうど第一次世界大戦直後である。
当時としては海軍大国イギリスの巡洋艦を真似た最先端の艦であったのであろう。
それにしても細い。まるで槍の穂先のようである。
鬼怒は長良型軽巡洋艦の3番艦として、長良、名取に次いで川崎重工神戸で完成、同型艦には五十鈴、阿賀野、由良がある。
当然、艦のコンセプトには第一次世界大戦の知見が反映されている。 |
 |
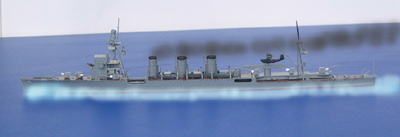 |
排水量は5500t、速度は36.5ノットという駆逐艦並みの高速である。
主な武装は古風な15㎝単装砲7門、魚雷発射管8であり、第二次世界大戦時の新造艦に比べると貧弱な印象を受ける。
開戦前には改装と装備強化のため、排水量は7000tほどまで増加し、その分、速度は低下した。
鬼怒は戦前は潜水戦隊旗艦を務めていたが、第二次世界大戦が始まるころには、姉妹艦ともども艦齢が20年にもなり、旧式の軍艦になっていた。 |
開戦時には第4潜水戦隊旗艦として、マレー上陸作戦を支援し、昭和17年からは物資、兵員の輸送やスラバヤ上陸軍の護衛、ニュギニア西部方面各地の攻略戦、陸軍部隊の輸送等に従事するなど大活躍した。
モデルは開戦時の姿である。この時点では、対空火器はほんのわずかしか搭載されていない。
 |
しかし、昭和18年6日23日爆撃で小破し、呉に帰港し補修を行った。この際、対艦戦闘用艦艇ではなく、防空巡洋艦としての大改造を受け、主砲を高角砲に交換、25㎜機銃38門搭載に増強される。
修理改修後、兵員、物資輸送作戦に徒事。昭和19年10日24日にはレイテ島オルモック湾に陸軍第30師団の兵員を載せた5隻の輸送船を護衛しマニラを出港、26日年前4時オルモックに無事到者する。
その帰路、米軍機150機の航空攻撃を受け、牛前11時30分、後部機関室左舷に直撃弾と至近弾3発を受けてしまう。しかし、防空巡洋艦としての能力を如何なく発揮し、10機以上を撃墜する敢闘を見せる。
|
しかし、被害により徐々に浸水が多くなりついに午後5時20分、総員退去の命令が下り、ビサヤン海バネイ鳥北西で沈没した。
乗員450名のうち、空襲で85名が戦死し、生存者は輸送艦に収容された。
23年間という長い艦命であった。
開戦時にはすでに旧式になっていた船ではあったが、役に立たなかった新鋭の軍艦が多い中、大活躍を演じた軍艦であった。
これは、水上戦闘想定を諦め、防空巡洋艦への転換が航空機主体となった海戦にマッチしたことが、戦閾、輸送、護衛に能力を発揮できた要因であろう。
上は水雷戦隊を率いる鬼怒。
軽巡洋艦 夕張
5500t級軽巡洋艦の装備を3000t程度の大きさの艦に詰め込んだコストパフォーマンスを追及した艦である。
全長:132.9m 最大幅:12.0mにすぎず大型の駆逐艦程度の大きさである。
高速艦であり、時速35.5ノットの速度を有した。
この艦を生んだきっかけは経緯は世界恐慌であり、予算が制限されるなかで、所定の性能の確保が必須となったことによる。
完成は大正12年(1923)7月であった。
これを実現した設計者は後に中将までなる技術軍人の平賀譲大佐であり、彼は後に軍艦設計の神様と呼ばれることになる。
しかし、この型の軍艦はこの夕張1隻に止まり、姉妹艦が建造されることはなかった。
日中戦争時には中国沿岸に派遣されて沿岸砲台の砲撃に活躍。
太平洋戦争では、第一次ソロモン海戦に参加し、米重巡ビンセンスに魚雷を命中させ、ルンガ岬沖海戦では輸送艦3隻を撃沈する戦果を挙げている。
昭和19年4月27日米潜ブルーギルの雷撃を受け、ルソン島付近で沈没。
兵装は14cm連装砲2基4門、14cm単装砲2基2門 、7.6cm高角砲1門 、魚雷発射管4門
であった。
艦の大きさのわりに重武装であるが、集合式煙突や連装主砲搭の採用、兵装の中心線配置などの工夫がされ、各国関係者を驚かせた。
しかし、小型の船体に多くの武装を施したため、船体に余裕がなく、対空戦闘能力強化が課題となった大戦後半では追加する余地がなく、主砲塔1基を撤去して設置せざるを得なかった。
航空巡洋艦 最上
航空巡洋艦として名高い。
しかし、それは晩年の姿であり、当初はロンドン軍縮条約の制限により8500t級の大型軽巡洋艦として設計された。
昭和10年7月28日に呉海軍工廠で竣工した。
姉妹艦に「三隈」「鈴谷」「熊野」があり、「最上級巡洋艦」と称されるシリーズのネームシップでもある。
軽巡として竣工したため、主砲は三連装5基、15門の15.5㎝砲が装備された。
この武装からして軽巡のものではなく、中巡と言えるものであった。
本格的な重巡として起工された高雄級に比べると艦橋が小さいのが特徴である。
竣工時のスペックは基準排水量11,200t、全長198m、幅18.45m、主機艦本式タービン4軸、出力152,000馬力、速力35ノット、主砲15.5㎝3連装5基15門の他、魚雷発射管12門であった。
電気溶接技術を用いて建造されたが、新造時からトラブルが続き、改修が相次いだ。
ロンドン軍縮条約が破棄されると20cm連装砲5基10門に換装される。
これにより基準排水量は12000tに増加する。なお、撤去した15.5㎝3連装砲塔は「大和」「武蔵」の副砲として転用されている。
太平洋戦争が始まると第7戦隊を編成し、南遣艦隊に所属し、バタビヤ沖海戦で連合国艦船6隻を撃沈する大戦果を上げる。
その後、インド洋での通商破壊作戦に従事する。
運命のミッドウェー海戦では、僚艦の三隈と衝突事故を起こし、1番砲塔より前部を切断し、さらに米機の攻撃で6発の命中弾を受け大破。
かろうじて内地に帰還するが、空母戦力の壊滅による航空戦力の補強と策敵能力の向上を目的に、後部砲塔2基を撤去し、飛行甲板を設置し、水上機11機を搭載できる航空巡洋艦に改装された。
この際、対空火器の増強とレーダーの装備も行った。
改造後、マリアナ沖海戦に参加し、昭和19年10月25日に西村艦隊の一艦としてスリガオ海峡で、米戦艦部隊と交戦し、被弾して戦場を離脱中、後続していた志摩艦隊の那智と衝突し、さらに米艦載機の攻撃により2発の命中弾を受け大火災となり放棄され、駆逐艦「曙」の魚雷で処分された。
この艦は衝突という2文字に呪われていたことになる。
なお、肝心の航空能力は当初搭載を予定した「瑞雲」の生産が進まず、零式3座水偵と零式復座水観を混載したが、数も揃わず、本来目的を果たすことはなくアイデア倒れのものになってしまった。
重巡洋艦 鈴谷
最上型巡洋艦の3番艦が鈴谷である。
ちなみにこの4姉妹は河の名を付けているが、鈴谷川なんて聞いたことがない。
それもそのはず鈴谷川は当時、日本領であった樺太を流れている川だそうである。
昭和10年(1935)に竣工したが、1番艦「最上」の船体強度不足による第四艦隊事件(艦首外板に大きなシワが生じた)のため、4姉妹は改善工事が施され、昭和12年(1937)に就役した
最上同様、昭和14年(1939)、主砲を15.5cm3連装から20cm連装砲に換装している。
開戦時は最上型重巡4姉妹は第7戦隊を編成し、マレー、スマトラ、ジャワ攻略戦の支援を行い、ミッドウェー作戦では姉妹艦の「三隈」を失う。
その後、第2次ソロモン海戦、南太平洋海戦を戦い、ラバウル方面への輸送、陸上支援と活躍する。
昭和18年(1943)に対空兵装強化を行い、マリアナ沖海戦後にさらに対空機銃の追加装備を行った。
最終的には25mm3連装機銃8基、同連装4基、同単装18基にまで強化された。
そして栗田艦隊に編入され、レイテ沖海戦に望んだが空襲で魚雷が誘爆し、沈没してしまう。 |
 |
重巡洋艦 鳥海
昭和7年に完成した日本の誇る大型巡洋艦、基準排水量は13140tあり、全長は204m 、速度は34ノットの高速性能があった。
主砲は20cm連装砲が5基であり攻撃力も大きい。同型艦に高雄・愛宕・摩耶がある。
現在のイージス艦を思わせるような巨大な艦橋が特徴。重厚で均整のとれたシルエットを持つ。
開戦後はマレー侵攻作戦支援に参加し、ボルネオ攻略戦に参加。昭和17年2月22日暗礁に触れ損傷。
27日、シンガポールで修理。修理完了後、インド洋で通商破壊作戦に従事し、商船2隻を沈める。
7月に第8艦隊旗艦となり、第1次ソロモン海戦に参加。連合軍艦隊を壊滅させるが、命中弾を受け戦死34名を出す。
昭和19年6月、マリアナ海戦に参加。
10月、レイテ海戦に参加し、同25日のサマール沖海戦で米軍機の空襲により大破。駆逐艦の魚雷で処分された。
駆逐艦 雪風
太平洋戦争の日本の艦艇で第一に名が出るのが、「大和」かこの「雪風」である。
日本の艦艇の多くが、「悲劇の」という形容詞が付き、大鳳、信濃、大和、武蔵ときりがないほどであるが、この雪風に付く形容詞は「幸運の」、「栄光の」である。
また、それにふさわしい実績を持つ。雪風は陽炎型八番艦として昭和15年1月20日佐世保工廠で竣工。
排水量2,000t、全長120mほどの小さな船に過ぎない。
速度はさすがに35ノットと速い。
主砲は12.7㎝連装砲3基他に25㎜連装機銃2基、61センチ魚雷4連装発射管2基を持つ。
開戦時には、ルソン島レガスピ攻撃を行い、ラモン湾上陸支援、セレベス、アンボン、チモール攻略に参加。
その後、スラバヤ沖海戦、ミッドウェー海戦、南太平洋海戦、第三次ソロモン海戦、ガ島撤退作戦に参加。
マリアナ沖海戦、レイテ沖海戦にも出撃し、僚艦が次々と沈む中で対空戦闘と乗員救助に奔走したが、この間、全く無傷であった。
昭和20年4月7日には沖縄特攻作戦にも参加したが、無事生還を果たし、稼動状態で終戦を迎える。
戦後は 復員船として活躍し、その後台湾海軍に引き渡された。 |
 |