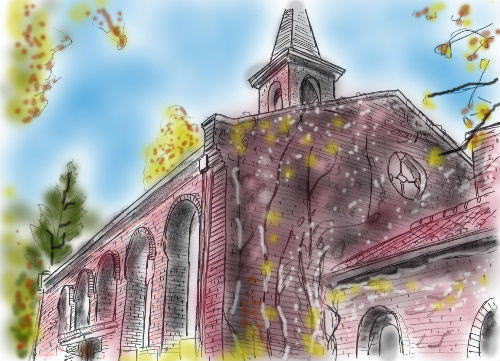その寺にこの国宝八角三重の塔がある。
この塔は鎌倉末期の建築といい、その姿が素晴らしい。八角形の形の屋根なのである。
最近の科学的年代測定では1290年代の建設であったと推定されている。
このような感じの塔は中国では見かけるが、現存している例は国内にはない。
塔は一番下に裳階(ひさし)がついているため、一見、四重塔に見える。
正確には「裳階付三重塔」というのだそうである。
また、縁や手すりもなく、板壁で、屋根を支える垂木が扇の骨のように放射状に外側に出ており、下から見上げるときのこの襞のように見える。
なぜ、こんな中国風の塔がここにあるかというと、当時の安楽寺住職の幼牛恵仁が中国生まれであり、故国の塔を思い出して建てたのではないかという。
そのバックは当時、塩田を支配していた鎌倉北条一族である。
この塔、山間の奥まった場所にひっそりと建っている。
その場所はかなりジメジメした感じの場所である。
意外に小さく感じたが、さすがに風格があり感動ものである。
この塩田の地も南北朝の騒乱や戦国時代の騒乱の舞台になった場所である。
それらを潜り抜け、現在までこれらの文化財が伝えられていることにも感心する。