

外国見館(石川町外国見)
本物?の外国見館は、間違えて突入した岡の谷津を挟んで北の岡に存在した。
こちらの館はどちらかというと居館的な感じであった。
この岡、東西に長く、東側が岡が切れており、巨大堀切状になっている。
岡の南北は谷津になっている。
西側が岡が続き、徐々に低くなって続いていく。
この館には東側から突入したのであるが、この方面は搦め手だったようである。
 |
 |
| 上が外国見館、下が外国見館Ⅱ |
岡の上から東の岡末端に向けて竪土塁が延びているが、これが登城路であったようである。
この竪土塁の周囲に段差2、3mの腰曲輪④が3段ほど構築される。
ここを越えると主郭直下の曲輪となるが、ここは平坦ではなく、斜面である。
ほとんど加工されていない。
 |
 |
 |
| ①主郭内部は若干西に傾斜している。 | ②主郭北西下にある横堀 | ③南に延びる尾根の曲輪群 |
その上の主郭①は東西50m、南北35mほどの広さであるが、若干西に傾斜しているがほぼ平坦である。
東側部分から南側に尾根状に突き出している箇所がある。
そこに長さ20mの土塁状の曲輪③が2つ並んでいる。
先端は腰曲輪になっており、下まで10mほどの急斜面である。
この尾根の付け根部から南に下る道がある。
 |
この道を下った場所が外国見館Ⅱの西の入口部近くである。 この道は外国見館Ⅱとの連絡通路かもしれない。 主郭の南側に犬走り、北側に帯曲輪があり、北側の帯曲輪は西側に続く台地につながっていく。 主郭の西側には深さ4mの横堀②が存在する。 がほとんど埋もれており肉眼では確認できるが、写真を撮るとよく分からない。 その西に曲輪が2つある。 外国見館Ⅱは西側の敵を想定しているが、この館は西側に対する防御が弱い。 その代わり、東側は湿地が存在した可能性があり防御は強そうである。 外国見館Ⅱとは全く逆である。 |
| ④館東側の段々状の曲輪 |
外国見館の西側に何が存在したのかは分からないが、外国見館Ⅱとは相互に補完しあい、ペアで敵と対する想定であったように思える。
航空写真は国土地理院が昭和50年に撮影したものを使用。

外国見館Ⅱ(石川町外国見)
石川町総合運動公園の北西1㎞にあるが、この地区、岡が浸食され凹凸ある複雑な地形をしており、場所が非常にわかりずらい。
だいたいの目星をつけて突入したのだが、一つ隣の岡であった。
つまり、間違い!でもあり正解でもあった。
どうやらここも城郭だった!
 |
 ↑ 北下の谷津から見た館跡。左の林が曲輪Ⅲ、少し低い林が曲輪Ⅱ、右が曲輪Ⅰ。 館は西から東に延びる細長い形をしており、長軸200m、短軸最大40mほど、けっこう大きい。 北側が深い谷津状になっており、深さ15mほどの鋭い切岸になっている。 |
しかし、南側はそれほどの深さはない。
東側は台地に続き高低差はない。
館は3つの部分からなり、東部、中央部、西部に分かれる。
東部の曲輪Ⅲ①は東の台地側に続くが、ここはどこまで城郭遺構か判断できない。
東西70m、南北最大40mほどの三角形をしており、北西側に緩く傾斜している。
南側が民家になっている。
さらに東にも続くようであるが藪でよく分からない。
この曲輪の末端には岩があり、下に小曲輪がある。
 |
 |
 |
| ①曲輪Ⅲ内部は西に少し傾斜している。 | ②曲輪Ⅱ内は植林で改変されていると思われる。 | ③曲輪Ⅰ内部、西端に土塁がある。 |
 |
 |
 |
| ④曲輪Ⅰの土塁は高さ1.5mほど | ⑤④の土塁の西側は深さ10mの堀切 | ⑥⑤の堀の北西側は段々状で虎口もある。 |
その下が中央部の曲輪Ⅱ②であるが、植林されており、不自然に平坦であるので、改変を受けている可能性もある。65m×20mの大きさである。
その西が主郭Ⅰ③であるが、55m×35mの大きさ。北西端に高さ1.5mの土塁④が長さ25m横たわる。
土塁の南側に虎口がある。
この土塁上に立って西側を見るとびっくり。
深さ10mの谷になっているのである。
この谷の底は堀切⑤になっている。
この谷は人工のものと思われる。
谷の北側は段々になっており、虎口のような場所⑥もある。
こちらの方面にも登城路があったと思われる。
この構造、鮫川の中野西館と良くにている。
この堀切の西側にも山があるが、ここにも遺構があるかもしれないが、確認していない。
この西側の構造からして、この西方面が敵を想定した方面であろう。
石川氏の本拠の三芦城の西方には防衛拠点がないが、この館は西の防衛拠点だったのではなかろうか。
あさこうじ館(石川町双里)
石川町中心街から西方向、社川近くに成亀温泉がある。
ここから石川町中心方向に500mほど東に進むと新屋敷地区である。
「新屋敷」という地名自体、館の存在を示唆しているが、まさにその通り館が存在する。
なお、この地の少し南に外国見館が存在する。
 |
新屋敷地区北側の岡に墓地がある。 その墓地の東側の少し高くなった部分が館跡である。 館といってもささやかな規模である。 しかし、幸いにも小さいながら完存なのである。 館域は東西70m南北40mほどに過ぎない。 南下の道路からは比高30mに過ぎない。 主郭①は45m×10mほど。東側が低くなっている。 北側に土塁がある。2m下に帯曲輪が一周する。 北側の幅は4mほど。 南側②は10mほど、さらに南下4mにもう1段、さらにその下にも曲輪がある。 多分、その下の民家が居館跡ではないかと思う。 |

↑は南側から見た館跡。左手の墓地から行ける。道路上の畑が居館跡だろうか?
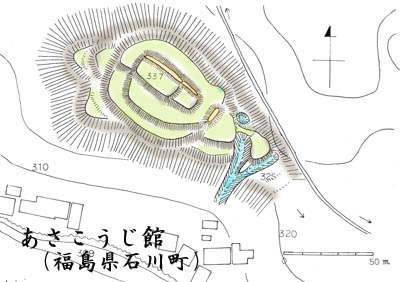
東側は帯曲輪の土塁を介し、東側に突出し15mほどの馬出のような曲輪があり、東端に井戸跡らしい穴③が2つあり、1つは下に竪堀状に溝が下る。
この館のある山の斜面は傾斜が緩く、この程度の防御機能では何もできない。
 |
 |
 |
| ①主郭内部は狭いが平坦できれいな状態 | ②南下の腰曲輪 | ③東下の腰曲輪には井戸跡と思われる穴がある。 |
精々、狼煙台、物見程度のものであるが、下の街道筋、それほど重要な街道とも思えず、物見をするほどのものが果たしてあるのだろうか?
石川氏家臣の前田氏の館という。
簗瀬館(石川町簗瀬)
石川町中心街から西方向、社川を望む東の岡の上にある。
阿武隈川西岸の滑津城跡から石川に向かう町道が社川を渡り、県道106号と合流するT字路の南東の岡である
この岡、社川付近の低地からの比高は40m程度であるが、社川が自然の水堀である。


社川に面した西斜面の斜面は急である。
南北は浸食され谷津状になっており、3方向が低地となっている。
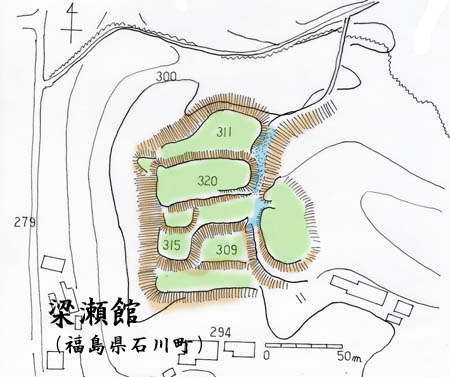
この東から突き出た岡先端が館跡である。
館には北側の谷津沿いに登る道から行く。
岡上部に出ると、館北側に虎口①のようなものが見える。
そこに通じる道を行くと館に入る。
この道は東側の山部を掘りきる堀切②兼用の道である。(この道の先には民家があり、そこで行き止まり。)
 |
 |
社川に面した西斜面の斜面は急である。 南北は浸食され谷津状になっており、3方向が低地となっている。 この東から突き出た岡先端が館跡である。 館には北側の谷津沿いに登る道から行く。 岡上部に出ると、館北側に虎口①のようなものが見える。 そこに通じる道を行くと館に入る。 この道は東側の山部を掘りきる堀切②兼用の道である。 (この道の先には民家があり、そこで行き止まり。) 館は主郭の南北に段を重ねる形式である。 主郭である曲輪③は70m×30mほどの大きさ。 |
| ①館北側の谷津から見た虎口 | ②主郭(右)東の堀底は道路になっている。 |
 |
 |
周囲は高さ4~5mの鋭い切岸になっている。 明らかに人工的に加工したものである。 主郭南北に腰曲輪があり、南側には5mほどおきに数段④存在する。 それらの曲輪は畑や水田に使われている。 東の山側は堀切兼用の道のみ。 畑があるが、あとは自然の山である。 この館は石川氏が社川、阿武隈川西方方向を監視するためのものであろう。 館主は石川有光の孫、和泉太郎光則という。 |
| ③主郭から見た東方向 | ④ 主郭から見た南下の腰曲輪 |